
お囃子

お囃子
まつりに華を添える笛、太鼓、鉦の音、軽やかな踊り手の舞
まつりに華を添える
笛、太鼓、鉦の音
軽やかな踊り手の舞
笛、太鼓、鉦の音
軽やかな踊り手の舞
川越まつりの囃子は、文化、文政の時代に江戸から伝わったもの。
源流はどれも、江戸の葛西囃子。
川越では以前からあった地元の里神楽と合流し古囃子として大成したといわれる。 もともと囃子は近郊の農村部が担当していた。
明治初期ごろより川越独自の改良を重ねて、今風の新囃子となり継承されてきた。


流派は王蔵流、芝金杉流、堤崎流に大別され、いずれも山車の移り変わりにともない、独自の改良を重ねて発展してきた。
笛1、大太鼓1、締太鼓2、鉦1の5人囃子に舞い手(踊り)が出る。リズムとメロディーは流派や囃子連によって異なるが、 多くの場面で笛がリードをつとめている。
曲目(舞)には屋台(天狐、獅子)、鎌倉(モドキ、オカメ)ニンバ、シチョウメ(モドキ、ヒョットコ)などがあり、 それぞれストーリーをもつ。


川越まつりのお囃子を代表する三大流派
川越まつりのお囃子を
代表する三大流派
代表する三大流派
おうぞうりゅう
王蔵流
王蔵流は川越南部に位置する中台地区の中台囃子連中が江戸末期に高井戸から神田祭で7台の山車の笛方を努めたという笛角を師匠に迎え、さらに、明治初期には王蔵金を師匠に迎え古囃子に手を加え創始したといわれる流派。


しばかなすぎりゅう
芝金杉流
芝金杉流
芝金杉流は川越南部に位置する今福地区の今福囃子連中が 五宿(調布市下布田)の師匠だった福岡仙松を師匠に迎え、 古囃子に手を加え創始した流派。


つつみさきりゅう
堤崎流
堤崎流は上尾市堤崎の吉澤菊次郎(天保6年~明治30年)が明治初期に隣村の木ノ下流の囃子に手を加え創始した新囃子といわれる。


川越市囃子連合会加盟団体 流派とその伝承経路
川越市囃子連合会加盟団体
流派とその伝承経路
流派とその伝承経路
川越市教育委員会「川越氷川祭りの山車行事 調査報告書・本文編」より一部引用 |
| 番号 | 団体名 | 流派の名称 | いつ どこから習ったか |
1 |
中台囃子連中 | 王蔵流 | 江戸末期に高井戸の笛角より、明治初期に王蔵金より |
2 |
小室囃子連 | 王蔵流 | 明治29年以前中台より、昭和22年再び中台より |
3 |
大塚新田囃子連 | 王蔵流 | 明治初期中台より |
4 |
南大塚囃子連 | 王蔵流 | 昭和21年地元の大師匠から習い復活 ※中台より。マモノは明治20年頃中台と一緒に下高井戸より習う |
5 |
岸町囃子連 | 王蔵流 | 古囃子があったが、昭和25年中台より習い復活 |
6 |
葵囃子連 | 王蔵流 | 昭和49年大塚新田より |
7 |
今福囃子連中 | 芝金杉流 | 明治初期、五宿(調布市)に由縁のあった福岡仙松より |
8 |
石田囃子連 | 芝金杉流 | 明治期北山田より |
9 |
寺尾囃子連 | 芝金杉流 | 今福より ※明治初期 |
10 |
砂新田囃子保存会 | 芝金杉流 | 明治中期今福より |
11 |
砂囃子保存会 | 芝金杉流 | 明治10年小中居より |
12 |
藤間囃子保存会 | 芝金杉流 | 明治中期寺尾より |
13 |
北山田囃子保存会 | 芝金杉流 | 明治33年今福より |
14 |
松龍會囃子連 | 芝金杉流 | 昭和47年藤間より |
15 |
新富町2丁目囃子連 | 芝金杉流 | 今福より ※昭和52年頃 |
16 |
住吉囃子連 | 芝金杉流 | 昭和55年藤間より |
17 |
仙波囃子保存会 | 堤崎流 | 大宮遊馬より |
18 |
府川囃子連 | 堤崎流 | 上尾市堤崎より |
19 |
浦島囃子連 | 堤崎流 | 昭和42年大仙波より、昭和43年南田島の荻原泰治より |
20 |
鈿女会囃子連 | 堤崎流 | 昭和42年頃小中居より |
21 |
幸町囃子会 | 堤崎流 | 昭和43年上尾市堤崎、安藤儀作他堤崎より |
22 |
連雀町雀会 | 堤崎流 | 昭和45年頃古谷本郷より |
23 |
古谷本郷囃子連 | 堤崎流 | 明治期と昭和47年上尾市堤崎より |
24 |
榎会囃子連 | 堤崎流 | 昭和48年雀会より |
25 |
南田島囃子連 | 堤崎流 | 明治30年上尾市堤崎より |
26 |
新宿町囃子保存会 | 若狭流 | 江戸時代菅間村より。明治2年飴売りコウさんより若狭流 ※菅間は明治20年頃堤崎流に変更 |
27 |
信亀会囃子連 | 若狭流 | 昭和49年新宿より |
28 |
久下戸囃子保存会 | 小村井流 | 明治の頃浦和西堀田島より移住した塩野伴次郎より |
29 |
今成囃子連 | 小倉井流 ※小村井流 |
明治初期久下戸より |
30 |
菊元会 | 葛西囃子 | 昭和37年頃、東京江戸川区岩楯孝次郎より |
31 |
竹生会 | 神田大橋流 | 昭和43年越生町本町より |
32 |
月鉾囃子連 | 木ノ下流 | 昭和45年坂戸市横沼より |
33 |
牛若囃子連 | 小村井流 | 昭和45年川島町飯島より、昭和47年吉見町飯島新田より |
34 |
小中居囃子保存会 | 堤崎流 | ※木野目、砂に伝えた |
35 |
鴨田囃子連 | 堤崎流 | 平成13年 府川より |
36 |
道真囃子連 | 堤崎流 | 平成15年 仙波より |
37 |
通町囃子保存会 | 木ノ下流 | 平成15年 川島町角泉より |
38 |
天神囃子連 | 芝金杉流 | 平成22年 石田より |
39 |
大手町囃子連 | 堤崎流 | 平成29年 設立 |
| 番号 | 団体名 | 流派 |
1 |
中台囃子連中 | 王蔵流 |
| 江戸末期に高井戸の笛角より、明治初期に王蔵金より | ||
2 |
小室囃子連 | 王蔵流 |
| 明治29年以前中台より、昭和22年再び中台より | ||
3 |
大塚新田囃子連 | 王蔵流 |
| 明治初期中台より | ||
4 |
南大塚囃子連 | 王蔵流 |
| 昭和21年地元の大師匠から習い復活 ※中台より。マモノは明治20年頃中台と一緒に下高井戸より習う |
||
5 |
岸町囃子連 | 王蔵流 |
| 古囃子があったが、昭和25年中台より習い復活 | ||
6 |
葵囃子連 | 王蔵流 |
| 昭和49年大塚新田より | ||
7 |
今福囃子連中 | 芝金杉流 |
| 明治初期、五宿(調布市)に由縁のあった福岡仙松より | ||
8 |
石田囃子連 | 芝金杉流 |
| 明治期北山田より | ||
9 |
寺尾囃子連 | 芝金杉流 |
| 今福より ※明治初期 | ||
10 |
砂新田囃子保存会 | 芝金杉流 |
| 明治中期今福より | ||
11 |
砂囃子保存会 | 芝金杉流 |
| 明治10年小中居より | ||
12 |
藤間囃子保存会 | 芝金杉流 |
| 明治中期寺尾より | ||
13 |
北山田囃子保存会 | 芝金杉流 |
| 明治33年今福より | ||
14 |
松龍會囃子連 | 芝金杉流 |
| 昭和47年藤間より | ||
15 |
新富町2丁目囃子連 | 芝金杉流 |
| 今福より ※昭和52年頃 | ||
16 |
住吉囃子連 | 芝金杉流 |
| 昭和55年藤間より | ||
17 |
仙波囃子保存会 | 堤崎流 |
| 大宮遊馬より | ||
18 |
府川囃子連 | 堤崎流 |
| 上尾市堤崎より | ||
19 |
浦島囃子連 | 堤崎流 |
| 昭和42年大仙波より、昭和43年南田島の荻原泰治より | ||
20 |
鈿女会囃子連 | 堤崎流 |
| 昭和42年頃小中居より | ||
21 |
幸町囃子会 | 堤崎流 |
| 昭和43年上尾市堤崎、安藤儀作他堤崎より | ||
22 |
連雀町雀会 | 堤崎流 |
| 昭和45年頃古谷本郷より | ||
23 |
古谷本郷囃子連 | 堤崎流 |
| 明治期と昭和47年上尾市堤崎より | ||
24 |
榎会囃子連 | 堤崎流 |
| 昭和48年雀会より | ||
25 |
南田島囃子連 | 堤崎流 |
| 明治30年上尾市堤崎より | ||
26 |
新宿町囃子保存会 | 若狭流 |
| 江戸時代菅間村より。明治2年飴売りコウさんより若狭流 ※菅間は明治20年頃堤崎流に変更 |
||
27 |
信亀会囃子連 | 若狭流 |
| 昭和49年新宿より | ||
28 |
久下戸囃子保存会 | 小村井流 |
| 明治の頃浦和西堀田島より移住した塩野伴次郎より | ||
29 |
今成囃子連 | 小倉井流 ※小村井流 |
| 明治初期久下戸より | ||
30 |
菊元会 | 葛西囃子 |
| 昭和37年頃、東京江戸川区岩楯孝次郎より | ||
31 |
竹生会 | 神田大橋流 |
| 昭和43年越生町本町より | ||
32 |
月鉾囃子連 | 木ノ下流 |
| 昭和45年坂戸市横沼より | ||
33 |
牛若囃子連 | 小村井流 |
| 昭和45年川島町飯島より、昭和47年吉見町飯島新田より | ||
34 |
小中居囃子保存会 | 堤崎流 |
| ※木野目、砂に伝えた | ||
35 |
鴨田囃子連 | 堤崎流 |
| 平成13年 府川より | ||
36 |
道真囃子連 | 堤崎流 |
| 平成15年 仙波より | ||
37 |
通町囃子保存会 | 木ノ下流 |
| 平成15年 川島町角泉より | ||
38 |
天神囃子連 | 芝金杉流 |
| 平成22年 石田より | ||
39 |
大手町囃子連 | 堤崎流 |
| 平成29年 設立 | ||
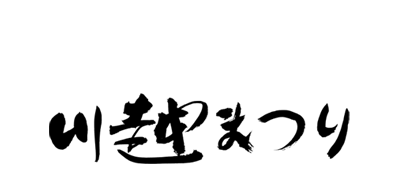
 概要/歴史
概要/歴史